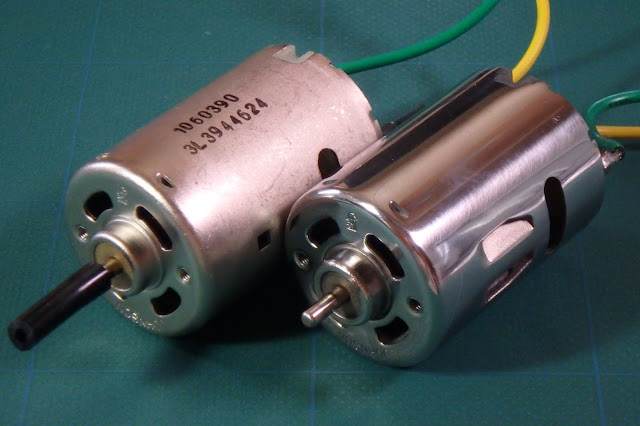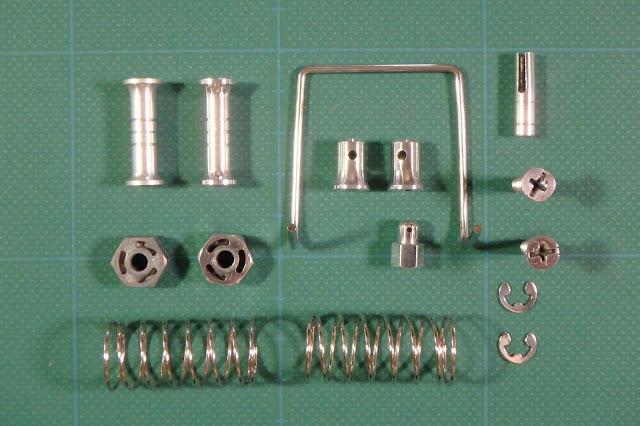受信器の位置を調整したり、載せ換えたりしていると、アンテナ線の付け根が傷み被覆が割れてちぎれそうになります。
修理に出せばいいのですが、簡単な延命方法を考えました。
※新品時に施せば、より効果的かもしれません
現状の受信機
SANWA RX-371です。どれもアンテナ線が付け根でちぎれそうです。
※受信は出来ています
材料と道具
厚さ1.0mmのPET板(ポリカーボネートでも可)、直径3mm一穴パンチ、アンテナパイプ(端切れで可)、写真にはありませんがアンテナパイプの先端を熱するもの(ライター等)
厚さ1.0mmPET板を3mm×3.5mmに切り出し、長辺端から5mm・短辺端から4mmの位置に印を付けます。
※写真では左上 縦に二本描いている二点鎖線は折り曲げる範囲 方眼は5mm
※形状は受信機によって異なります
一穴パンチで穴を開けます。
二点鎖線の間を曲げます。
※Rの大きさは、受信機のアンテナ線が出ている部分と同じくらい
アンテナパイプの加工
必要な長さにカットする前に先端をライター等で熱します。
熱すると樹脂が溶けて、少し丸く膨らみます。
※熱し過ぎに注意!燃えないように!!
PET板のR内側、アンテナパイプの熱していない方から差し込みます。
※入り難い場合は、丸棒ヤスリやリーマーなどで穴のエッジを落とします。
加熱して丸くなった部分がストッパーとなり、抜けない状態で止まります。
任意の寸法でアンテナパイプをカットします。
※写真は5mm程度
側面内側に両面テープを貼ります。
R内側からアンテナ線を通します。
アンテナ線の付け根位置を合わせて、両面テープで固定します。
アンテナ線の付け根にストレスがかかりにくくなります。